
「チームの雰囲気を、なんとか良くしたい…」🤔
「部下にもっと主体的に動いてほしい…」
「管理者として、本当にこのやり方で合っているんだろうか…」😥
チームのために日々悩み、試行錯誤を重ねる中で、ふと孤独を感じていませんか。その重圧を、一人で抱え込んでしまっているのではないでしょうか。
もしかしたら、最近よく耳にする「心理的安全性」という言葉に、「またその話か…」「理想論はもう聞き飽きた」と、少しうんざりしているかもしれません。
その気持ち、とてもよく分かります。現場は、そんな簡単な言葉で片付けられるほど甘くはありませんよね。
ですが、もし、その「心理的安全性」という言葉の向こう側にある、明日からすぐに使えて、確実にチームの空気と部下の表情を変える「具体的な技術」があるとしたら、少しだけ耳を傾けてみませんか?✨
この記事は、小難しい理論を解説するためのものではありません。日々、現場で奮闘するあなたに寄り添い、「これなら自分にもできそうだ」と思っていただける具体的なヒントを届けるためのものです。
大丈夫です。あなたは決して一人ではありません。この記事が、あなたの強力な味方になることをお約束します。💪
▼ この記事のポイント
なぜ「安心できる場所」が、チームの力を最大限に引き出すのか?
なぜ「安心できる場所」が、チームの力を最大限に引き出すのか?
少しだけ、「心理的安全性」、つまり「チームという安心できる場所」について考えてみましょう。
「こんな初歩的な質問をしたら、無能だと思われるかも…」
「ミスを報告したら、厳しく叱責されるに違いない…」
もし、あなたのチームのメンバーが、常にこんな不安を抱えていたらどうでしょうか。彼らは挑戦を恐れ、言われたことだけをこなすようになり、本来持っているはずの能力を発揮できなくなってしまいます。
実は、これは単なる想像の話ではありません。厚生労働省をはじめとする多くの調査で、退職理由の上位には常に「職場の人間関係」がランクインしています。ある調査では、会社に伝えなかった本当の退職理由の第1位が「人間関係が悪い」(46%)という衝撃的な結果も出ているのです。
このような状況は、誰よりもチームを預かるあなた自身が、一番辛いのではないでしょうか。
一方で、「このチームでは、何を言っても大丈夫だ」という安心感があれば、事態は一変します。
Google社の有名な調査「プロジェクト・アリストテレス」が証明したように、心理的安全性の高いチームは、そうでないチームに比べて離職率が低く、生産性が高いことが分かっています。メンバーは素朴な疑問や新しいアイデアを臆せず口にし、ミスが起きても隠さずに「学びの機会」として共有してくれます。
活発な意見交換が、これまで生まれなかった革新的なアイデアや問題解決の糸口を生み出すのです。🌱
つまり、チームという「安心できる場所」を作ることは、遠回りのようで、実はチームの成果を最大化するための、データにも裏付けされた確実な近道なのです。
信頼を築く第一歩。「肯定の言葉」で心を開く
では、どうすれば「安心できる場所」を作れるのでしょうか。その鍵は、あなたが日々使う「言葉」にあります。
私たちは、部下を想うあまり、ついこんな言葉を使ってしまいがちです。
- 😥「なんで、まだ出来てないの?」
- 😥「そのやり方はダメだよ」
忙しい中で、つい口から出てしまう気持ちもよく分かります。しかし、これらの「否定の言葉」は、相手に「自分は責められている」と感じさせ、心を固く閉ざさせてしまいます。
今日から、ほんの少しだけ意識して、これを「肯定の言葉」に変えてみてはどうでしょうか。
「肯定の言葉」への変換ヒント📝
(つい言いがち)😥「なんで、まだ出来てないの?」
(試してみてほしい言葉)😊「進捗はどうかな?もし困っていることがあれば、力になるよ」
(つい言いがち)😥「そのやり方はダメだよ」
(試してみてほしい言葉)😊「なるほど、そういう視点もあるんだね。ちなみに、こういう方法だと更にスムーズかもしれないよ」
(つい言いがち)😥「報告書、誤字が多すぎるよ」
(試してみてほしい言葉)😊「報告書ありがとう、助かるよ。データが分かりやすいね。一点だけ、ここの誤字を直すと、もっと完璧な資料になるよ」
ポイントは、まず相手の行動や意見を「そうか」と一度受け止めること。その上で、「私はこう思う」「こうしてくれると助かるな」と、あくまであなたの意見として伝えるのです。
この小さな変化が、部下との間に信頼という名の橋を架け始めます。✨
部下の「できた!」を育てる。「勇気づけの褒め方」
「安心できる場所」をさらに強固にするもう一つの武器が「褒め方」です。それは、部下を勇気づけ、次の一歩を踏み出すエネルギーを与えるための技術です。
結果だけを見て「すごいね!」と褒めるだけでは、部下は「結果が出せない自分はダメなんだ」とプレッシャーを感じてしまいます。
大切なのは、結果だけでなく、その裏側にある「努力のプロセス」や「工夫した行動」に光を当てること。
部下を勇気づける褒め方の3つのヒント💡
具体的な「行動」に焦点を当てる👏
(△)「プレゼン、良かったよ」
(〇)「プレゼンお疲れ様。特に、クライアントのニーズを想定して、事前にデータを3パターンも準備していたあの行動が素晴らしかった。だからこそ、鋭い質問にも自信を持って答えられたんだね」
→ 「私の行動を、ちゃんと見ていてくれたんだ!」という喜びが、次の挑戦への意欲につながります。
「成長した点」を言葉にする🌱
(△)「資料作成、うまくなったね」
(〇)「半年前は苦労していたけど、今回の資料はグラフの使い方も的確で、格段に進歩していて本当に驚いたよ。素晴らしい努力だね」
→ 「自分の成長を認めてもらえた!」という実感ほど、大きな自信になるものはありません。
チームへの「貢献」に感謝する🙏
(△)「議事録ありがとう」
(〇)「いつも詳細な議事録を素早く共有してくれて、本当にありがとう。おかげでチーム全体がスムーズに動けている。本当に助かっているよ」
→ 「自分の仕事が、誰かの役に立っている!」という実感が、仕事のやりがいと誇りを育みます。
【特別コラム】あなたのチームを変える、たった一つのシンプルな原則
ここまで、部下との信頼関係を築くための具体的な方法をお伝えしてきました。最後に、そのすべてのテクニックの根底に流れる、たった一つの、しかし最も重要な原則を、ある偉大な言葉とともにご紹介します。
まず理解に徹し、そして理解される。— スティーブン・R・コヴィー(『7つの習慣』著者)
この言葉は、人間関係における「黄金律」とも言えるものです。私たちはつい、自分の正しさや意見を先に伝えたくなります。自分のことを「理解してほしい」という気持ちが先行してしまうのです。
しかし、コヴィー博士は、その順番が逆だと説きます。「まず、相手を理解することに全神経を集中させなさい」と。
この記事でご紹介した「肯定の言葉」を思い出してみてください。相手の言葉を否定せず「そうか」「なるほど」と受け止めるのは、まさに『理解に徹する』ための第一歩です。また、具体的な「褒め方」も、部下の行動や努力の背景を深く『理解』しようとしなければ、決して出てこない言葉のはずです。
もし、あなたが部下との間に見えない壁を感じているとしたら、それはこの「順番」が逆になっているだけなのかもしれません。
明日から、部下と話す前に、ほんの一瞬だけこの言葉を思い出してみてください。「まず、相手を理解しよう」と。その小さな意識の変化が、あなたのリーダーシップを、そしてチームそのものを根底から変える、強力な力を持っているのです。
まとめ:頑張るあなたへ。焦らず、あなたのペースで。
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます。
コヴィー博士の言葉にもあったように、チーム作りの根幹にあるのは、やはり「人」との向き合い方です。そして、その関係性を育むのが、日々のコミュニケーションに他なりません。
どうか、一度にすべてをやろうと気負わないでください。
完璧な管理者なんて、どこにもいません。
まずは明日、部下に声をかける時に、たった一つでいいので「肯定の言葉」を使ってみる。あるいは、誰かの小さな頑張りを見つけて、具体的に褒めてみる。
その、あなたの小さな一歩が、チームの空気を変える確かな一歩になります。部下の表情が少し和らぐ、会話が一つ増える。そんな小さな変化が、あなたの自信にもつながっていくはずです。
あなたがチームのために悩み、奮闘していること。その背中を、部下はきっと見ています。
焦らず、気負わず、あなたのペースで。
私たちは、あなたの挑戦を心から応援しています。💪✨
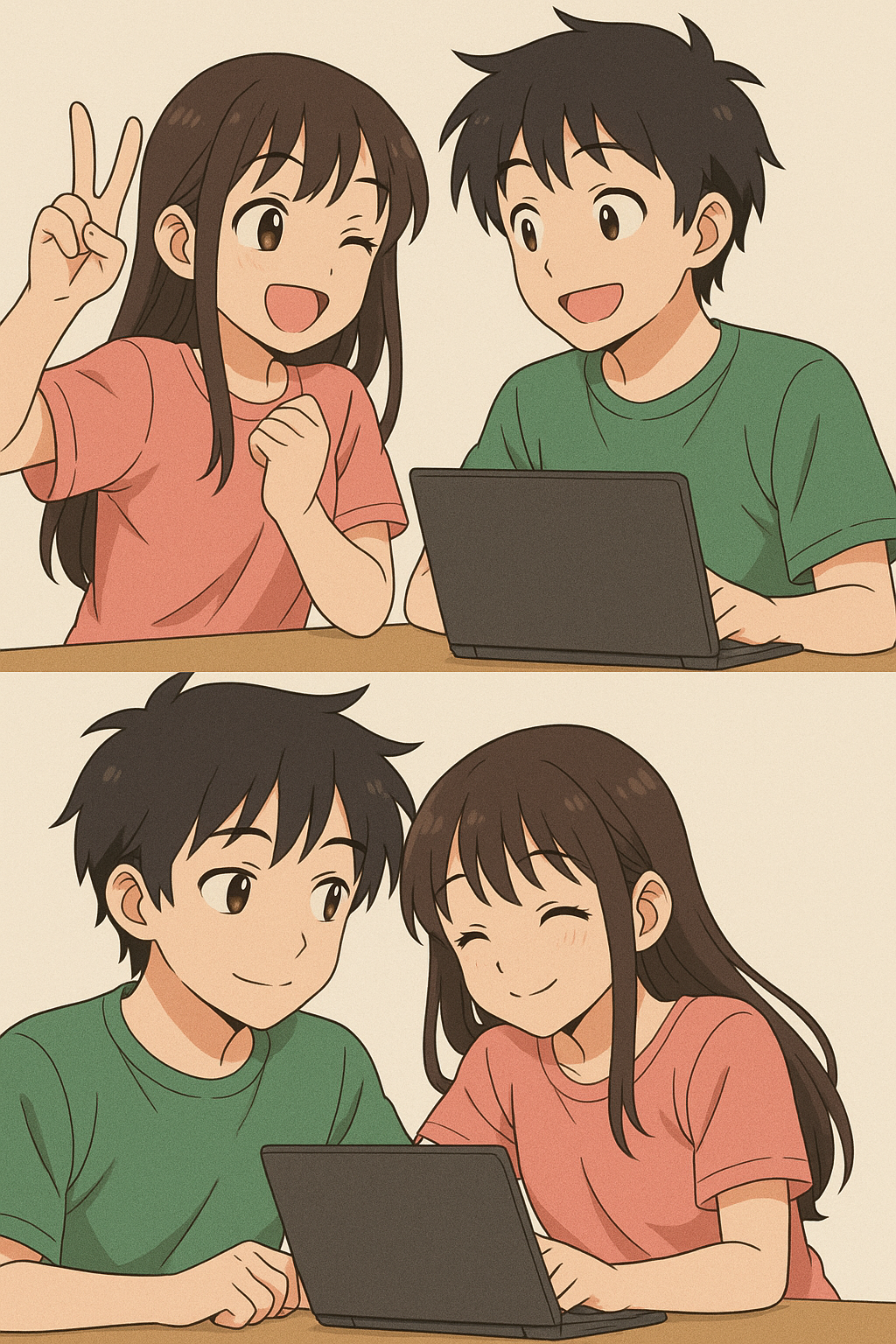


コメント